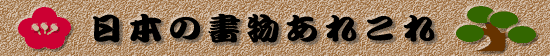|
野坂さんが現在、といっても少し前の文壇の様子を書かれています。登場するのは、三島由紀夫、澁澤龍彦、丸谷才一、吉行淳之介、五木寛之などの面々。簡単に言えば、永六輔さんのような作詞家やラジオの脚本作家から始まり、雑文を書くようになり、小説を次々と発表して直木賞を受賞するまでの道のりです。「おもちゃのチャチャチャ」を作詞した、エロ映画を上映した、歌手として日本全国のキャバレーをまわりながら小説を書いたという面白いエピソードもあります。
文壇酒場を転々とし、そこで飲んでいる小説家を冷徹な眼で観察し、本質を鋭く見透かしています。三島由紀夫については、その付き合いを含めてしばしば記述されていますが、「三島は、〜つまり近代日本語を信じていない、さんざ装飾過多を指摘され、退廃した文体といわれながら、なお固執したのは、むしろその空しさを強調するためじゃないのか。」という箇所は独自の三島論だと思います。「文壇」とは?「小説家」とは?という問いの答えを模索する日々が続きます。
そして、「小説家」というものになりたいと常に願い、いくつかの小説を書いてもまだ小説家になりきれない、及ばないと焦りの気持ちが何度も何度も書かれています。『火垂るの墓』を書いては、小説家にさえ許されないいかがわしい大嘘であるといううしろめたさを長い間、引きずります。
「「変わった種族」で目を引く。〜小心そのもの、他人の表情を気にして、怯えつつの世渡り、いい加減、嘘つき、出鱈目が売物、そして、時に「だが根は真面目」といわれれば、正体見破られてはアウトと認めつつ、心中、うれしい気持がある。チャランポランは世を忍ぶ仮の姿、実はと奇妙な見栄だが、さて、「小説家」に近づいてみると、彼らは、おそろしく真面目に思える、ぼくの、いかがわしさは、仮面じゃなく、本性じゃないのか。〜誰ともうちとけることができない、小説が人間全般の営みを描くものだとすると、ぼくは、自分しか書き得ない、マスターベーションに近い。」この自己描写はこの本のなかでも白眉と言えます。
三島由紀夫や澁澤龍彦も絶賛した「ノサカ文体」。その何ものにも似ていない独特なリズムは読みはじめると心地よくなってきます。『野坂昭如コレクション』、『野坂昭如リターンズ』(国書刊行会)という箱入りの格好よい集成が出ています。若いころの黒眼鏡の渋い写真が載っています。
|