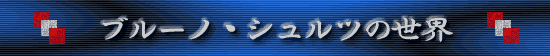|
古今東西、多くの文学者が旅をテーマにした作品を残していますがシュルツにも旅の話があります。それが今回紹介する「砂時計サナトリウム」です。シュルツ作品の中では比較的筋がはっきりと起承転結を追うもので、ポーランドの映画監督ヴォイチェフ・ハースの手で1971年に映画化されています(邦題「砂時計」)。
物語は旧式な汽車が、ある街へ到着する場面から始まります。その汽車というのが大変風変わりで、車室の中は迷路のようになっていて、座席は高すぎるので数人しかいない客は床の上に座り込んでいるのです。汽車は蒸気の音もたてず、駅舎もなにもない駅にゆるゆると停まります。
主人公ユーゼフは、この街のサナトリウムに療養している父を見舞いにやって来たのです。ユーゼフは汽車を降り、暗い森の中を通り、サナトリウムへ向かいます。この間の風景の描写は神秘的で、さすが画家でもあった作家の手によるものだと思わせるものがあります。
さて、このサナトリウムでは、「瀕死の患者の時間を後退させ、回復の可能性に手をつける」という治療をしています。つまりこのサナトリウムはこの世とあの世の境界にただよっているような、特殊な世界にあるのです。タイトルの「砂時計」とはポーランド語で klepsydra といい、「死亡通知」という意味も持っています。サナトリウムだけでなく、街じたいも死の世界に近い、不気味な雰囲気に満ちています。
ユーゼフは父とともにサナトリウムに滞在しますが、次々と怪奇な現象に遭遇します。しだいにそこでの生活は耐えがたいものとなり、ついにユーゼフは父を見捨て、街から逃げ出すべく汽車へ乗り込みます。
しかし彼はもと居た世界に戻れず、汽車に居着くようになります。主人公はお古の鉄道員の制服を恵んでもらい、客車で歌を歌って小銭を稼ぐ零落の身となってこの物語は終わります。
初めてこの短編小説を読んだとき私は日本の昔話「うらしまたろう」を思い出しました。一度異界を旅したものはもう元の世界には戻れない、という寓話としても読むことができる作品です。
|