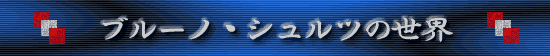|
私が子供の頃(20数年前)、鳥を飼っている家は今よりも多かったような気がします。近所の友達の家や、床屋や小さな店には九官鳥、文鳥などの鳥がいました。我が家でも、めじろ、うずらなど次々と鳥を飼っていました。最近は自分が大人になったせいか、あるいはマンション暮らしのせいか、めったに鳥に会いません。残念です。
シュルツの第一短編集「肉桂色の店」の3番目に収められている「鳥」は、鳥を飼うことに憑かれた父の物語です。
父の鳥に対する情熱は、まず鳥の卵を孵すことから始まります。世界各地の動物商から鳥類の有精卵を取り寄せ、雌鳥に抱かせて雛を孵すのです。雛たちは成長しペリカン、孔雀、雉やコンドルになり、屋根裏部屋は鳥の王国と化してゆきます。その一方で、父は違う種類の鳥たちを結婚させ、新しい種類の鳥を孵すことに夢中になります。父は鳥への情熱にはまりきったためか、次第に自分自身すらも鳥じみてきます。手の形は鳥の趾のようになり、コンドルと尿瓶を共用し、家族の前でもうっかり鳥のしぐさ、啼き声を発し、きまり悪げにしたりします。
そんな父の鳥の王国にもある日突然終わりがやってきます。大掃除の日、女中のアデラが現れ、糞の山が築かれたその有様に仰天し、箒を振り回して鳥たちを追い出します。アデラに頭の上がらない父は、失意の中、悄然と部屋を後にします。
この話には後日談があって、短編集「肉桂色の店」の最後に収められている「大いなる季節の一夜」の中で、アデラが追い払ったあの鳥たちの子孫が戻ってくるのです。鳥たちの思いがけない帰還に父は有頂天になって喜びますが、その鳥たちは、あるものは頭が2つで、あるものは片翼だけで弱々しく飛んでいます。しかも街のならず者が鳥たちに向かって石つぶてを投げ始め、父の制止の声も空しく、一羽残らず墜落してしまいます。しかし、地上に落ちた鳥たちの骸を見てみると、それらは紙細工であり、野牛の毛や羽毛を貼り合わせてどうにか鳥に見せかけていたもだったのでした。
シュルツの鳥の描写は一貫して悪魔的で不気味ですが、その中を右往左往する父の姿がいかにも滑稽で健気で笑いをさそいます。
|