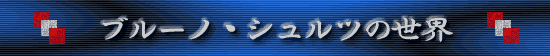|
「わたしたちは日常の言葉を操作しているうちに、それらがいにしえの永遠の物語の断片であることを、そして、神々の彫刻や像のかけらで家を築いていることを忘れている。・・・・・わたしたちのイデーには神話から生まれていないようなものはこれっぽっちもない、それは変形され、変質されてしまった神話学に他ならない」 エッセイ『現実の神話化』より
シュルツの小説を読んでいると、このひとは才能があるから書いたというよりは、書く必要があって書いたという印象を受けます。
シュルツは23歳のとき、第一次世界大戦で家を焼かれ、その翌年に敬愛していた父を亡くします。帰るべき家を失ったシュルツにとっておそらく創作こそが自分の居場所、故郷となったのでしょう。
一連の小説に繰り返しあらわれるモチーフは、子供時代を過ごした街、天体、列車、広場、馬車、商店であり、そしてその舞台に登場する人物は父、母、女中のアデラといったおそらくシュルツの周りにいた人々をモデルにしています。
そしてそれらの物語は単に再現されたものではなく、シュルツの手によって個人的な神話として再生されたものです。シュルツにとって失われた子供時代を神話化することは、自分を救済することに等しかったにちがいありません(シュルツの大人になってからの生活は病気、貧困、人種差別などの苦労が絶えなかった)。
エッセイ『現実の神話化』はシュルツが自身の文学観を語ったものです。
スラブ語圏は伝統的に言語学が盛んな地ですが、シュルツもその影響を受けてか、言葉に対するなみなみならぬ思いが語られています。シュルツにとっての言葉とは「万物を包含する統合的なある古き神話の断片、残骸」であると書いています。
そして詩とは「言葉の祖地への憧れ・・・・・原初の神話の急激な再生」であるとしています。
別のところでは芸術について次のように言っています。「芸術の役割は、名のないもののなかに投げこまれたゾンデ(測深機)となることです。芸術家とは価値の創られている深部のプロセスを記録する装置なのです。」シュルツがもう少し遅く生まれていたらシュルレアリスムの重要な作家に位置付けられていたかもしれません。
シュルツの小説が、作家の子供時代に材をとりながら、回顧的ではなく、独特の深さと普遍性を感じさせるのは、このような文学観あってのことなのでしょう。
参考文献 『もっと知りたいポーランド』
第8章 ポーランドのユダヤ人とユダヤ文学 (板倉千鶴著)
|